「STO(セーフティトルクオフ)機能があるから、サーボドライブに電磁接触器はもういらない」
FA(ファクトリーオートメーション)業界の設計に携わる方なら、一度はこんな話を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
確かに、STO機能の登場は安全回路の設計に革命をもたらし、コスト削減や制御盤の省スペース化に大きく貢献しています 。しかし、この「電磁接触器は不要」という言葉を鵜呑みにしてしまうと、思わぬ安全上のリスクを抱え込むことになりかねません。
本記事では、数多くのメーカーの技術資料や国際安全規格を徹底的に分析し、現代のサーボシステムにおける電磁接触器の真の必要性について、専門家の視点から深く掘り下げて解説します。安全と生産性を両立させるための、本質的な設計思想に迫ります。

- 某電機メーカーエンジニア
- エンジニア歴10年以上
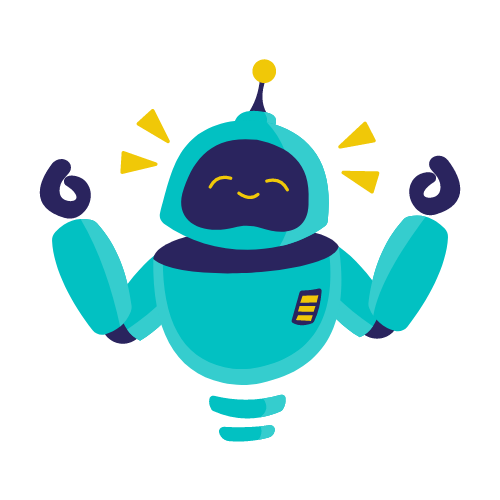
第1章:基本の確認!サーボドライブと電磁接触器の役割
まず、基本に立ち返りましょう。ACサーボドライブは、上位コントローラからの指令に基づき、サーボモータの位置・速度・トルクを極めて高精度に制御する電子装置です 。
電磁接触器は、電磁石の力で物理的に接点を開閉するスイッチです 。PLCなどからの低電力信号で、サーボドライブのような大電力負荷の主電源を安全にオン・オフする役割を担います 。この二つのコンポーネントの関係性を正しく理解することが、安全設計の第一歩となります。
第2章:なぜ「電磁接触器は不要」と言われるのか?STO機能の登場
近年、「機能安全」という考え方が機械安全の主流となり、ISO 13849-1などの国際規格が整備されました 。この流れの中で登場したのが、サーボドライブに内蔵された**セーフティトルクオフ(STO)**機能です 。STOは、ドライブ内部の電子回路でモータがトルクを発生させるためのエネルギー供給を安全に遮断する機能です 。これにより、従来「予期せぬ起動の防止」のために必要だった2重の電磁接触器とその複雑な配線が不要になりました 。さらに、STO作動時はドライブの主電源はオンのままなので、安全が確認されれば即座に運転を再開でき、ダウンタイムを大幅に短縮できるという大きなメリットがあります 。このコスト削減と生産性向上のインパクトから、「STOがあれば電磁接触器は不要」という言説が広まったのです。
 ろぼてく
ろぼてくたしかに”予期せぬ起動の防止のため”には、STOがあれば電磁接触器は不要です。
第3章:STOの限界と電磁接触器の「本当の役割」


しかし、STOは万能ではありません。その限界を理解することが極めて重要です。STOの最大の限界点は、感電からの保護を提供しないことです。STOはドライブの「出力」を電子的に止めるだけで、入力側の電源端子や内部のコンデンサには高電圧がかかったままです 。SMCのマニュアルでも「STO機能では感電の危険性を取り除くことはできません」と明確に警告されています 。
また、STOはドライブ自体が致命的なハードウェア故障(内部短絡など)を起こした場合には無力です。三菱電機のマニュアルが警告するように、このような故障時に電磁接触器がなければ大電流が流れ続け、火災に至る危険性があります 。ここに、電磁接触器の現代における真の役割があります。それは、「メンテナンス時の確実なエネルギー遮断(感電防止)」 と「ドライブ故障時の火災防止(装置保護)」という、STOではカバーできない根源的な安全を確保することなのです。



STOはモータの不慮の再起動を防ぐ役割で、電磁接触器は感電防止と火災防止の役割です。明確に役割が違うのです!
第4章:【結論】最適な安全設計とは?STOと電磁接触器の賢い使い分け
結論として、現代のサーボシステムにおける最適な安全アーキテクチャは、**STOと主電源用電磁接触器を組み合わせた「ハイブリッド構成」**です。これは、両者の長所を活かし、短所を補い合う「多層防御」の考え方に基づいています。
- STOの役割(機能安全):ライトカーテンやドアスイッチと連動させ、日常的に発生しうる危険(作業者の侵入など)に対する「予期せぬ起動の防止」を担当します。これにより、高い安全レベル(PL/SIL)と生産性を両立します。
- 電磁接触器の役割(電気安全・装置保護):システムの起動・停止、そして最も重要な「メンテナンス時の感電防止(ロックアウト・タグアウト)」と「ドライブ故障時の火災防止」という、物理的なエネルギー遮断を担当します。
この役割分担こそが、安全で、各種規格に準拠し、かつ生産性の高いシステムを構築するためのベストプラクティスと言えるでしょう。
| 安全・保護タスク | 主たる責任 | 副次的・バックアップ | 関連規格・原則 |
| モータの予期せぬ起動の防止 | STO機能 | 電磁接触器 | ISO 13849-1, IEC 61800-5-2 |
| メンテナンス時の感電保護 | 電磁接触器 / 断路器 | (なし) | IEC 60204-1, LOTO |
| ドライブ内部短絡・火災からの保護 | 電磁接触器(アラーム連動) | 上流の遮断器 | メーカー指示 , UL/CE |
| システムの電源オン・オフ | 電磁接触器 | – | – |
第5章:主要メーカーの考え方は?(三菱電機、安川電機、オムロン)
メーカー各社の資料を詳細に読み解くと、表現に違いはあれど、その根底にある安全思想は共通しています。
- 三菱電機は、STO機能により「電磁接触器を2個削減できる」とアピールしつつも、回路例では「サーボアラーム用」として1個の電磁接触器を残しています 。さらに旧機種のマニュアルでは、故障時の火災防止のために電磁接触器の設置を義務付けています 。
- 安川電機は、標準配線例として主回路用の電磁接触器を明記しており、これが基本構成であることを示しています 。
- オムロンの資料では、「STOには感電防止機能はないため、メンテナンス時にはブレーカーやコンタクタ等によるエネルギー源からの切り離しが必要」と、電磁接触器の必要性が極めて明確に記述されています 。
これらの事実から、「STOが不要にするのは**『機能安全のための冗長な安全用接触器』であり、『電気安全と装置保護のための主電源用接触器』**は依然として必須である」という、業界共通の認識が見えてきます。
第6章:まとめ:安全と生産性を両立する設計のために


今回の調査で明らかになった点を、改めてまとめます。
- 「STOがあれば電磁接触器は不要」は誤解:STOが代替するのは「機能安全」のための安全用接触器であり、主電源を物理的に遮断する役割は代替しません。
- 電磁接触器は依然として必須:特に「メンテナンス時の感電防止」と「ドライブ故障時の火災防止」という、最も基本的な安全確保のために不可欠です。
- ベストプラクティスは「ハイブリッド構成」:STOの「生産性」と電磁接触器の「根源的な安全性」を組み合わせることで、最も堅牢なシステムが実現します。
- マニュアルの熟読が重要:設計の際は、マーケティング的な表現だけでなく、必ずメーカーが提供する詳細な技術・安全マニュアルを確認し、その指示に従ってください。
コストや効率も重要ですが、安全は何物にも代えがたい価値があります。本記事が、皆様のより安全で信頼性の高いシステム設計の一助となれば幸いです。



設備のコストダウンを考えると、目につくのが電磁接触器です。ただし、電気に対しての安全を考えると電磁接触器は必要不可欠な存在なのです!







コメント